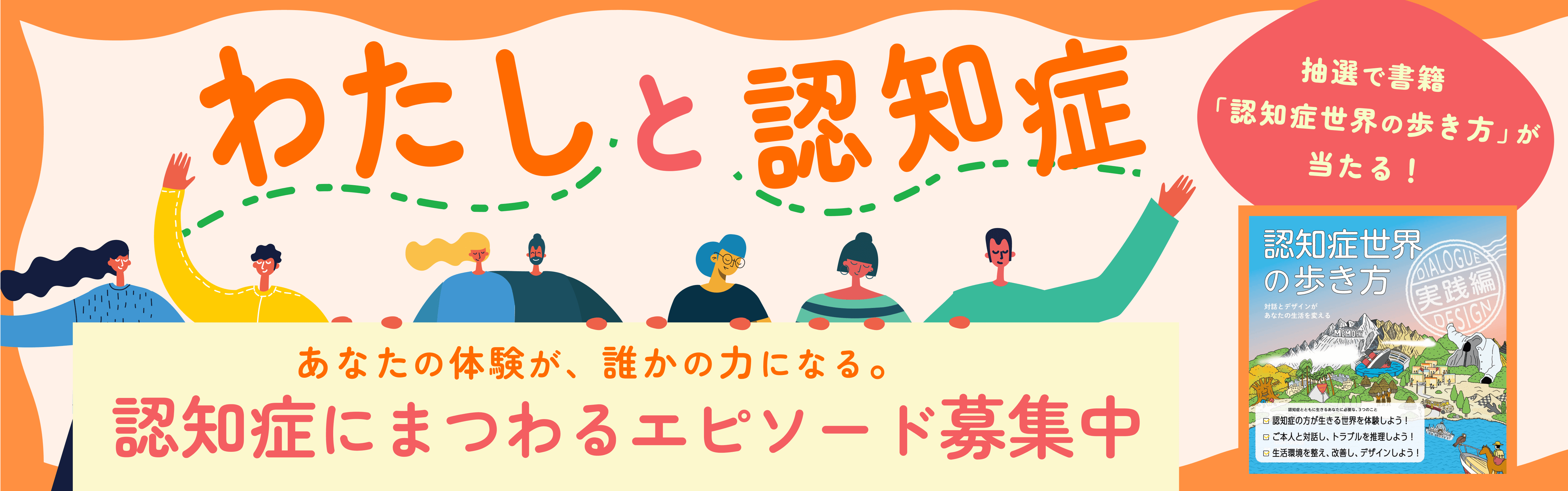「眠りが浅くて夜中に何度も目が覚めてしまう」、「ベッドに入ってもなかなか眠れない…」など睡眠の悩みを抱えた経験はありませんか。
年齢を重ねるにつれて眠りが浅くなり、睡眠時間が短くなったと感じることはあるかもしれません。
この記事では眠りが浅い人の特徴や原因、改善方法について解説していきます。
不眠症との関係
就寝時に眠りが浅い状態が続き、日中の生活に支障がでる場合「不眠症」と診断されます。不眠症は入眠障害と中途覚醒、早朝覚醒の大きく3つに分けられます1。
入眠障害(入眠困難)
入眠障害(入眠困難)とは布団に入った後、しばらく眠れない状態です。入眠障害の原因は多岐にわたり、ストレスなどの精神的な要因のほか、就寝前にスマートフォンを使用したり、カフェインを含む飲み物を摂取したりすることも関係します。また、眠れないことを気にしすぎて余計に緊張してしまい、さらに眠れなくなって悪循環におちいってしまう場合も少なくありません。
中途覚醒
中途覚醒は、一度寝付いた後に何度も目が覚める状態です。再び寝ても浅い眠りとなり、翌日に疲労感が残ります。加齢や就寝前の飲酒などによって起こりやすく、頻尿や咳、かゆみなどの身体的な症状によって引き起こされる場合があります。
早朝覚醒
早朝覚醒は、予定の起床時間よりも早く目覚めてしまい、その後再び眠ることができなくなる状態です。特に高齢者に多く見られ、朝の3時頃に目が覚めてしまうケースもあります。翌日には眠気で長時間の昼寝につながり、夜間の睡眠リズムをさらに乱す恐れがあります。
加齢との関係
眠りが浅くなるのには、加齢が関係している場合もあります。加齢とともに眠りが浅くなる原因は以下の3つに大きく分けられます。
- ・ 睡眠の質が低下している
・ 睡眠障害が起きている
・ 認知機能が低下している
詳しく見ていきましょう。
睡眠の質が低下している
加齢に伴い、人間の睡眠パターンは変化するのが一般的です。高齢者は若年者に比べて早寝早起きの傾向が強くなり、睡眠の質も低下します2。
通常、人間の睡眠サイクルは深い眠りのノンレム睡眠と浅い眠りのレム睡眠を交互に繰り返します。高齢者の場合はノンレム睡眠が減少し、レム睡眠が増加する傾向にあります。この変化により、高齢者は物音や尿意などの刺激に敏感になり、目覚めやすくなってしまうのです。さらに、眠気を感じていなくても習慣的に布団に入る傾向があり、これが入眠障害を引き起こす一因にもなっています2。
睡眠障害が起きている
以下のような睡眠障害は、浅い眠りに直接影響を与え、睡眠による休養感を低下させることがわかっています。
- ・ 睡眠時無呼吸症候群(睡眠中に呼吸が止まってしまう病気)3
・ レストレスレッグス症候群(睡眠中に異常感覚によって脚を動かしてしまう病気)4
・ 周期性四肢運動障害(睡眠中に手足のぴくつきが無意識に起こる病気)5
・ レム睡眠行動障害(睡眠中に夢と同じ行動をする病気)6
これらの睡眠障害がみられる場合は、適切な治療をおすすめします。特に睡眠時無呼吸症候群やレム睡眠行動障害は、将来の認知症リスクを高める可能性があると報告されているため、早期の医療機関受診が望ましいです7,8。
認知機能が低下している
認知症の当事者の多くは睡眠が浅く、さまざまな不眠症状を経験します。認知機能の低下により、体内リズムが崩れ、夜間に連続して眠ることが困難になります。その結果、昼夜逆転のような睡眠パターンの乱れが生じることも珍しくありません2。
このような状況では、日中に適切な刺激を与え、規則正しい生活リズムを維持することが睡眠の質を改善するうえで重要です。認知機能の低下と睡眠障害は互いに影響し合うため、両方に対するケアが必要となります。
浅い眠りを改善する方法
浅い眠りを改善する方法として、以下が挙げられます。
- ・ 決まった時間に就寝・起床する
・ 適度な運動を習慣化する
・ ストレス解消法を取り入れる
・ 寝室の環境を取り入れる
・ 寝る前のお酒やカフェインの摂取を避ける
毎日質の高い眠りにつけるように、これらを実践していきましょう。
決まった時間に就寝・起床する
浅い眠りを改善するには、体内時計を整えるために、毎日一定の時間に就寝して起床することが大切です。長時間の昼寝や夜ふかしは避け、平日も休日も同じリズムを保つことで、自然な睡眠サイクルを確立できます1。
適度な運動を習慣化する
ウォーキングや軽いランニングなどの定期的な運動は、睡眠の質を向上させる効果があります9。特に夕方から夜の時間帯にかけての運動は、運動で上昇した体温が就寝時間に向けて徐々に低下するため、自然な眠りが促されます。
一方で、就寝直前の激しい運動は、交感神経を活発にさせ、かえって寝つきを悪くする可能性があるため、なるべく避けた方が良いでしょう。
ストレス解消法を取り入れる
ストレスは不眠症の大きな要因になります。このため自分に合ったストレス解消法を見つけ、日常的に実践することが大切です。ヨガや読書、音楽鑑賞など、リラックスできる活動を毎日のルーティンに組み込むことで、心身の緊張をほぐし、良質な睡眠につながります1。
寝室の環境を整える
快適な睡眠環境を整えることも重要です。室温は20℃前後、湿度は40〜70%が理想的です。照明は暖色系の(温かみのある色合いの)蛍光灯を使用し、就寝前は徐々に明るさを落としていくと良いでしょう。枕は首のすきまに合い、汗を吸収する素材のものを選び、マットレスは背骨が自然な状態を保てる適度な硬さのものが望ましいです10。
寝る前のお酒やカフェインの摂取を避ける
就寝前のアルコール摂取は、睡眠の質の低下につながります。また、カフェインの過剰摂取(1日400mg以上、コーヒー約700ml相当)は、夜間の睡眠をさまたげる可能性があります11。就寝の数時間前からはこれらの摂取を控え、代わりにハーブティーなどのカフェインフリーの飲み物を選ぶことがおすすめです。
ご自分の睡眠習慣が気になる方は、こちらのチェックリストも活用してみてください。
まとめ
眠りが浅くなるパターンは大きく3つあり、日常生活に支障をきたすこともあります。年齢を重ねると浅い眠りに移行しやすくなってしまいますが、生活習慣の改善や睡眠環境の見直しをすることで改善するケースもあります。今できることから対策を始めて、健康的な生活を送りましょう。