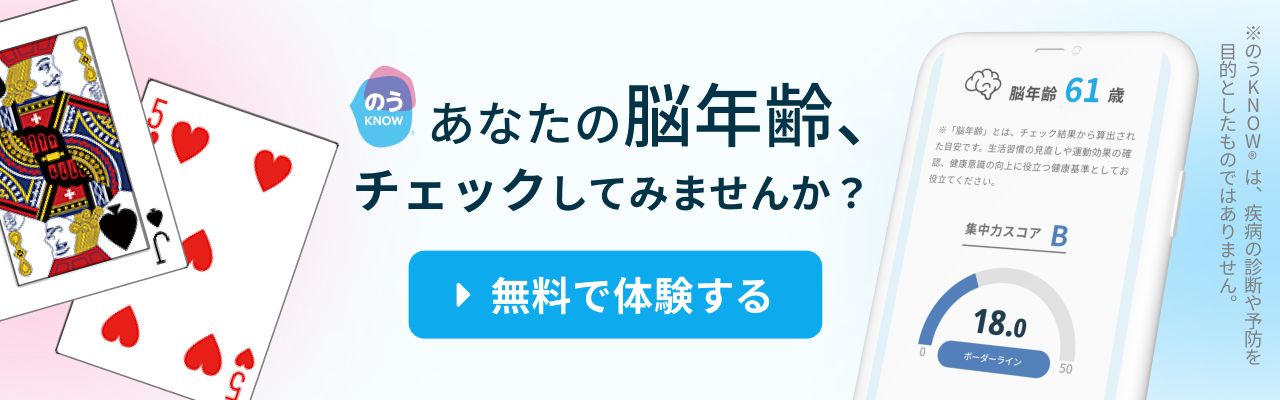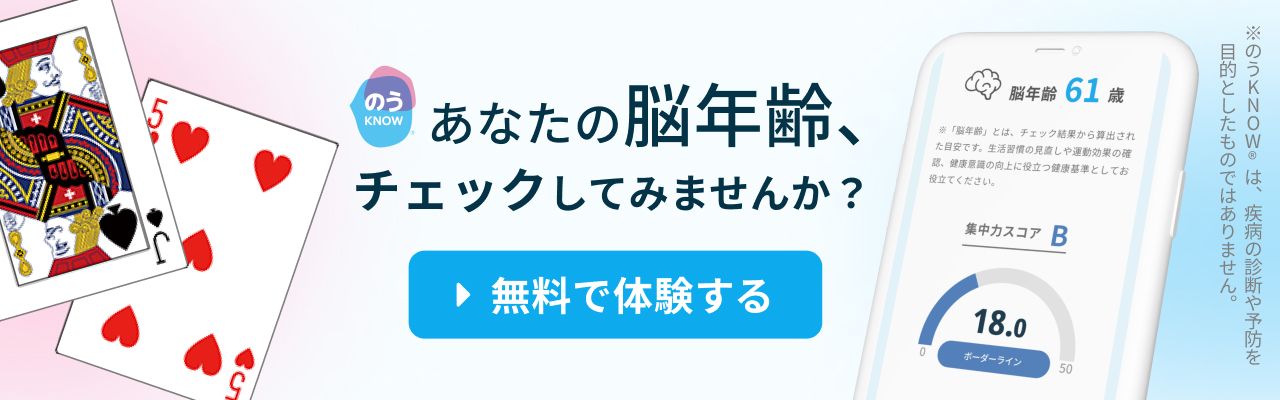「フレイル」「サルコペニア」「ロコモティブシンドローム」。テレビの特集などでそれぞれの言葉を聞いたことがあっても、意味の違いを説明できる方は少ないのではないでしょうか。
この記事では、混同して使われていることも多いこれらの言葉の意味や予防について解説します。
フレイルとサルコペニア・ロコモティブシンドロームの違い
フレイル、サルコペニア、ロコモティブシンドロームは、どれも高齢者の健康にかかわる重要な用語ですが意味は異なります。
それぞれの用語の意味を表にまとめました。
用語 |
意味 |
|---|---|
フレイル |
加齢により心身が衰え、将来的に要介護状態になるリスクが高まったり、社会的な問題が出てくる状態です1。 健康な状態と要介護の状態の間にあるとされ、フレイルに早めに気づき適切に対応することで健康な状態に改善できる可能性があります。 |
サルコペニア |
加齢により筋骨格量が減少し、筋肉の身体機能が低下する状態です。広背筋・腹筋・膝伸筋群・臀筋群などの筋力低下が起こり、立ち上がることや歩くことに消極的になります。高齢者の活動低下の大きな原因となっています2。 |
ロコモティブシンドローム |
加齢による運動器の障害によって日常生活における移動機能が低下し、介護が必要となるリスクが高くなっている状態です。略して「ロコモ」とも呼ばれています3。 |
フレイル・サルコペニア・ロコモティブシンドロームの関係性
フレイル、サルコペニア、ロコモティブシンドロームはそれぞれ定義が異なる概念ですが、加齢に伴い筋肉が衰える(サルコペニア)ことで、歩くことが難しくなり(ロコモティブシンドローム)、外出が消極的になることで心身が弱っていく(フレイル)というようにそれぞれ関係があります。
これらの状態は、放置することで健康寿命を低下させ、要介護や寝たきり状態になるリスクを高めるため、早期からの対策が重要です。
フレイル・サルコペニア・ロコモティブシンドロームの予防
フレイル、サルコペニア、ロコモティブシンドロームのいずれについても、定期的な運動を行うことと、栄養バランスの良い食事を摂ることが予防に効果的であると言われています2, 4, 5。
定期的に運動する
ウォーキングやジョギングなどの定期的な有酸素運動に加え、筋肉に抵抗をかけるレジスタンス運動が効果的とされています6。
日本整形外科学会は、ロコモティブシンドロームの予防のために片脚立ち(左右とも1分間で1セット、1日3セット)とスクワット(5〜6回で1セット、1日3セット)を毎日行い、筋力とバランス能力を同時に鍛える方法を紹介しています7。
筋トレをすることに高いハードルを感じる方は、普段の生活で階段を利用する、傾斜のある道を歩く、近い距離はできるだけ徒歩で移動するなど、簡単な運動から意識して取り入れてみてください。ご自身に合った安全な方法で無理をせずに行いましょう。
栄養のバランスの良い食事を摂る
身体的フレイル、サルコペニアやロコモティブシンドロームの予防として、十分なエネルギー摂取に加え、タンパク質の適切な摂取が必要です。
これらの予防には、1日体重1kgあたり1.0〜1.2g(体重50kgの方であれば、50〜60g)のタンパク質の摂取が推奨されています2, 8。
また、多様な栄養素の摂取や筋量・身体機能の低下抑制に関わることから、フレイル対策において食品摂取の多様性の意義は大きいとされています9。多くの品目を摂取できるよう、日々の食事を工夫しましょう。
社会参加の機会を増やす
フレイルでは、社会参加の機会が減少することが最初の入り口になりやすいため、趣味やボランティア、就労などの機会をもつことが推奨されています4。
高齢者は、経済的な困窮や定年退職、パートナーとの死別などがきっかけで孤独を感じやすくなり「社会的フレイル」と呼ばれる状態になることがあります。そのような状態は、単に孤立しているだけではなく、心身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。
次のような活動を通して社会とのつながりを持つことはフレイルを予防するうえで重要です。ご自身が無理なく楽しく続けられる活動を見つけましょう。
・就労
・習い事
・ボランティア活動
・友人や家族との食事
・地域活動や趣味の集まりへの参加
「どこに行ったらいいかわからない」「何をしたらいいかわからない」という方は、地域の自治体などが主催している高齢者向けの教室や集まりに参加してみるのも1つの選択肢になるでしょう。
まとめ|フレイル、サルコペニア、ロコモティブシンドロームの違いとは?
フレイル、サルコペニア、ロコモティブシンドロームは、高齢者の健康に関わる異なる概念で、それぞれ異なる意味を持つ用語です。フレイルは心身の衰えによる要介護リスクの高まり、サルコペニアは加齢による筋力低下、ロコモティブシンドロームは運動器の障害による移動機能の低下を指します。
健康な高齢期を過ごすために、まずは日常生活で階段を使う、近所を散歩する、片足立ちを試すなど、無理のない運動を取り入れることから始めてみましょう。そして、食事の面では、タンパク質を意識的に摂取し、多様な食材を取り入れることを心がけましょう。
早めの予防と対策が、自立した生活を長く続けるための鍵となるでしょう。