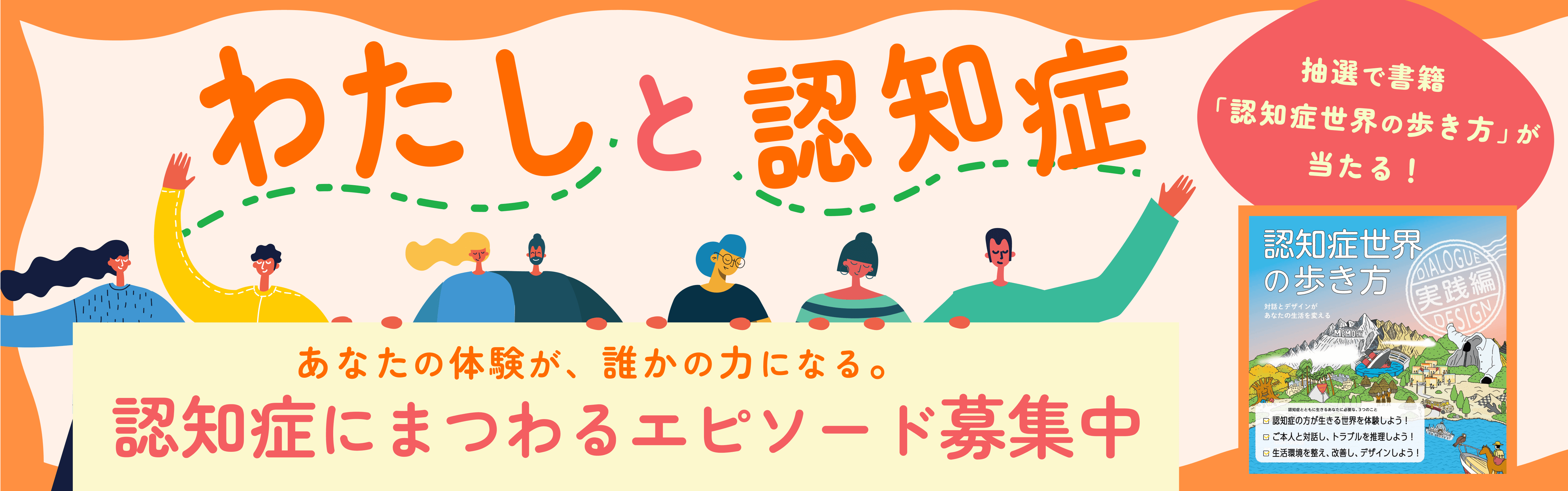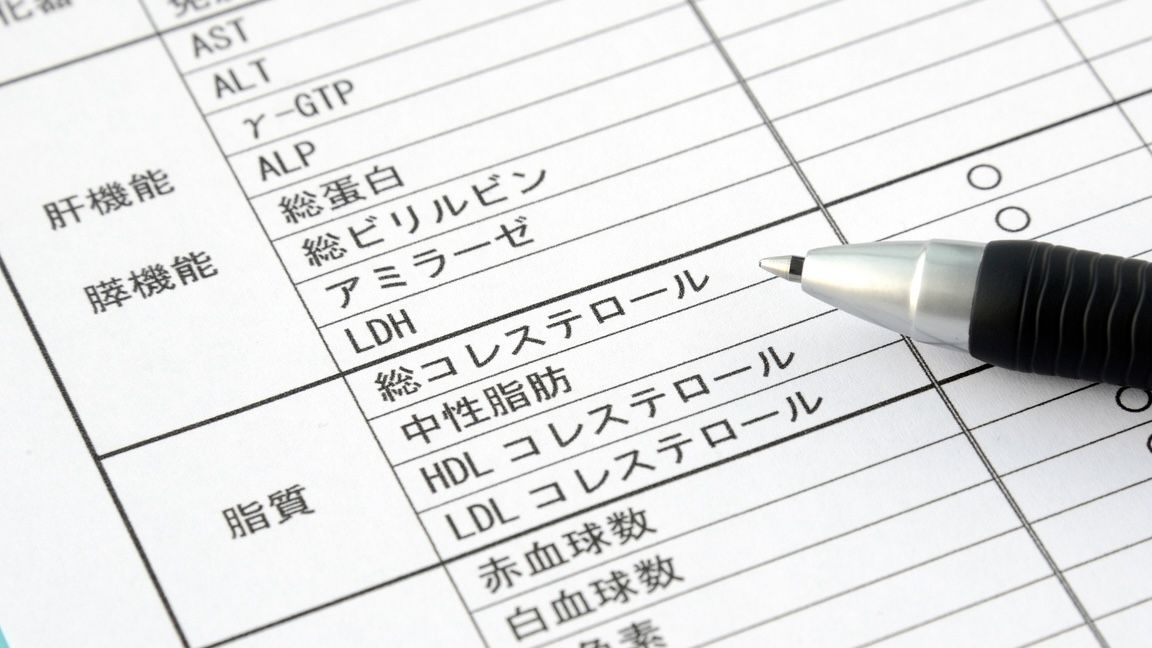ご自身が高血圧であることがわかったとき、どの診療科を受診すればよいのか迷う方も多いでしょう。高血圧は、認知症や心疾患、脳血管障害などのリスク因子であるため、早期に治療や生活習慣の改善をはかることが重要です1, 2。
本記事では、医療機関の選び方や受診のタイミングについて、詳しく解説します。
高血圧の症状と受診の目安
高血圧は動脈のなかを流れる血液が血管の壁に及ぼす圧力(血圧)が継続的に高い状態を指します3。自覚症状がでないことも多いため、定期的な検診や血圧の管理を継続的に行うことが重要です。早期に治療が受けられるよう、受診の目安を知っておきましょう3。
高血圧について
高血圧になったとしても症状はゆっくりと進行するため、初期の段階で体調の変化に気づくのは困難です。ただ、高血圧が長期間にわたって続くと、心臓や血管に負担がかかり、心筋梗塞や脳卒中などを引き起こす可能性があります3。
また、若年期から中年期の高血圧は、認知機能低下のリスクを高めるという報告もあります1。
高血圧の具体的な数値は以下の通りです2。
収縮期血圧※1 |
拡張期血圧※2 |
||
|
診察室血圧 |
140mmHg以上 |
かつ/または |
90mmHg以上 |
|
家庭血圧 |
135mmHg以上 |
85mmHg以上 |
(文献2を参考に表を作成)
※1 診察室血圧:病院の診察室で測定した血圧。
※2 家庭血圧:自宅で測定した血圧のこと。診察室血圧と家庭血圧は異なることがしばしばあります2。
医療機関では、状態や生活習慣を総合的に評価し、適切な治療方針を決定します。
高血圧の自覚症状について
高血圧は「サイレントキラー」とも呼ばれ、多くの場合、明確な自覚症状がありません。頭痛やめまい、肩こりなどが起こることもありますが、これは血圧に関係なくあらわれる症状でもあるため、自覚症状のみでは判別が困難です3。
そのため、健康診断や定期健診などで見つかるケースが多く見られます。
高血圧で受診すべきタイミング
医療機関への受診を検討するタイミングは以下の通りです。
- ・家庭血圧が135/85mmHg以上の状態が続く
・健康診断で高血圧を指摘された
・家族歴に高血圧がある
・肥満や運動不足など、生活習慣の改善が必要
なお、180/120mmHg以上の著しい高血圧や、急激な血圧上昇を伴う頭痛・悪心・嘔吐・胸痛などの症状がある場合は緊急性が高いため、すぐに医療機関を受診する必要があります4。
高血圧では何科を受診すればいい?
初めての受診では、内科や循環器内科を受診するのがよいでしょう。
今までの経過や診察内容も併せて判断できるため、まずはかかりつけの内科で相談しましょう。内科は全身の健康状態を総合的に診る診療科で、生活習慣病全般の管理を得意とします。内科で心臓合併症の精査が必要と判断された場合は、必要に応じて循環器内科などへの紹介も行っています。
循環器内科は、心疾患の専門家として、より専門的な検査や治療に対応できます。
また、二次性高血圧という他の疾患による高血圧の可能性もあります。急に血圧が高くなった、急に体重が増えたなどあれば、ホルモン異常の有無を調べるために内分泌内科受診も検討しましょう。
高血圧での医療機関の選び方
高血圧の治療は、クリニックなどの一般診療所と総合病院のどちらでも受けられますが、総合病院は重症合併症の診断治療を主に行います。そのため、まずは診療所を受診し、必要に応じて総合病院へ紹介してもらうようにしましょう。
高血圧を放置するとどうなる?
高血圧を放置すると血管に持続的な負担がかかり、さまざまな合併症のリスクが高まります。合併症は適切な血圧管理により予防できる可能性があります。
主な合併症には脳卒中(脳梗塞・脳出血)、心臓病(狭心症・心筋梗塞・心肥大・心不全)、慢性腎臓病などがあります3, 5。
高血圧を悪化させないために日常生活で気をつけたいこと
高血圧を悪化させないためには、生活習慣の見直しが非常に重要です。
日常生活で気をつけたいポイントは、①減塩、②食事パターンの改善、③適正体重の維持、④運動 、⑤節酒、 ⑥禁煙、⑦ストレスの管理などが挙げられます6。
血圧をコントロールし、合併症のリスクを減少させるためにも、できることから改善していきましょう。
食事療法と塩分管理
食塩は血液量を増やし血圧を上昇させるため、必要以上に多く摂取すると心臓に負担をかけます。そのため、日本高血圧学会のガイドラインでは、1日の食塩摂取量を6g未満に抑えることを推奨しています6。塩分の含まれる調味料や加工食品は控えめにしましょう。
飽和脂肪酸やコレステロールが多く含まれる食事は、動脈硬化や血流悪化を引き起こし、血圧を上昇させるリスクを高めます。そのため肉類や乳製品のとりすぎにも注意が必要です5。
野菜や果物などのカリウムを多く含む食品を摂取することで、血圧を低下させる効果が期待できますが、慢性腎臓病などでカリウムの制限が必要な場合は、主治医との相談が必要です。塩分や脂肪分の摂取を減らし、野菜や果物、全粒穀物を多く取り入れ、バランスの取れた食事を心がけましょう。
運動習慣の重要性
運動療法は血流をスムーズにし、血圧を低下させます6。また、体重管理やストレス軽減により、全身の健康状態の改善にもつながります。運動療法のポイントは、定期的かつ継続的に行うことです。
具体的な方法は以下の通りです。
- ・有酸素運動(ウォーキング・ステップ運動・スロージョギング・ランニングなど)をできれば毎日行う6
・1回10分以上で合わせて1日40分以上の運動を継続的に実施する
・自分の体力に合わせた運動強度を選択する
ただし、心臓や脳に関する持病がある場合は、運動を制限されることがあるため、主治医と相談しながら無理のない範囲で運動を続けましょう。
ストレス管理の方法
心理的・社会的ストレスによって、高血圧の発症が2倍以上高まるといわれています6。ストレスがかかると、身体の防御機能が過剰に働き、本来の休息や睡眠の力が弱まります。
ストレスを解消し、身体の機能を正常に保つためには、運動・睡眠・休息・食事などのバランスが取れていることが重要です。
1日15分、ウォーキングや体操などをすることで身体の緊張をほぐし、リラックスできるとされています7。毎日十分な睡眠をとりましょう。不眠が続く場合は要注意です7。無理をせず活動の合間に休息をとり、気持ちをリフレッシュさせ、心にもゆとりと栄養を補給しましょう。
また、栄養バランスのとれた食事を心がけ、三食を味わって楽しく食べることが重要です。
身体の調子を整えることは、心の調子をよくすることにもつながります。ご自身の生活で、無理をしすぎていないか一度振り返ってみませんか。
まとめ:高血圧で悩んだときは、まず内科か循環器科を受診しましょう
早期診断と適切な治療を受けることで、効果的に血圧を管理し、関連する健康リスクを減少することにつながります。また、よりよい血圧コントロールのために、食事、運動療法などの生活習慣の改善のアドバイスももらえます。
ご自身が高血圧であることがわかったとき、どの診療科を受診すればよいのか迷った場合は、近くの内科や循環器科を受診することを検討してみましょう。