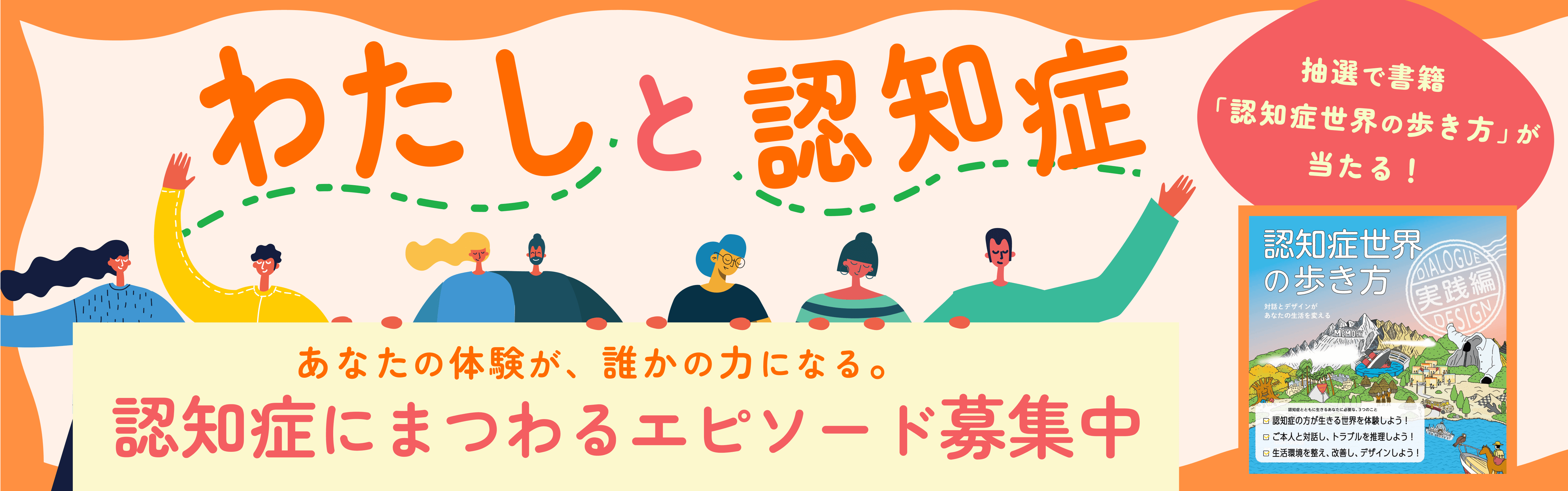少子高齢化社会の雇用のあり方を考える「シニア雇用研究所」。この特集記事では、シニア人材の活躍を後押しするためのヒントを、企業の取り組みや成功事例から探っていきます。
初回は、三谷産業株式会社(以下、三谷産業)の取り組みを紹介します。同社は1928年、石川県金沢市にて創業。総合商社でありながら、メーカーやコンサルティング機能も有し、多様化する顧客ニーズに応えつづける先進的な企業です。
事業成長とともに雇用体制の強化にも力を入れてきた三谷産業。2021年4月からは「無期限の継続雇用制度」を導入しました。一人ひとりが描くキャリアデザインや健康状態を考慮しながら、60歳以降の社員に働く場所を提供しています。
同社で2025年4月より人事本部長を引き継いだ林原大輔さんに、制度を制定した経緯や脳の健康に関する対応策、シニア雇用に対する展望など幅広くお話を伺いました。
お話を伺った方
-
三谷産業株式会社
執行役員 人事本部長
林原 大輔さん1999年4月三谷産業入社。設備サブコン部門である空調首都圏事業部にて建設現場の設計・施工・保守業務に従事。
2019年より執行役員事業部長として事業部員のモチベーション向上と快適な職場環境の実現を目指し、独自の制度や施策を推進。
2025年4月に人事本部へ異動。現場経験を活かした人事本部長として、全社的な制度改革に取り組んでいる。三谷産業株式会社:https://www.mitani.co.jp/
シニア活躍には“自助努力”が必要──たどり着いた「新しい終身雇用」の形
──三谷産業では、かなり早い段階からシニア雇用施策に取り組んできたと聞いています。まず、「無期限の継続雇用制度」を施行した理由からお聞かせいただけますか。
林原さん:従来とは違う「新しい終身雇用制度」をつくりたいと考えたのが、新制度策定のきっかけでした。
当社では60歳以降、65歳まで嘱託社員として働ける「定年後の継続雇用制度」を2006年から導入していましたが、だんだんと「シニア社員自身が仕事に対して向上心を持ちにくい」という課題が浮き彫りに。雇用が保証されているという安心感に加え、旧制度の嘱託社員には評価制度やそれに伴う昇給、賞与がないことに起因していると分析しました。
さらに、組織上の問題で言うと、役職定年を設けていなかったためにマネジメント層の若返りが滞っていて。
そこで、役職定年は設けつつ、60~65歳までは昇給・賞与のある「マスター正社員」、66歳からは賞与のある「マスター嘱託社員」として雇用する新制度を導入しました。
出典:三谷産業グループ マスター社員・継続雇用制度のご紹介資料
──年齢に制限なく働けるというところに、会社としての懐の深さを感じますね。
林原さん:「無期限の継続雇用制度」という名称から、そう受け取る人は少なくないかもしれませんね。もちろん、会社として支援は惜しみませんが、実は“自助努力”も必要な、本人にとって少々厳しめの制度設計となっているんです。
60歳以降の配属先は、本人と各部署との合意を経て決定されます。例えば「これまでと同じ部署で、同様の業務がしたい」という自身の意向があっても、部署のニーズに応えられるスキルや人柄でなければ、マッチングは成立しない。組織に受け入れてもらえるための“自走力”が該当社員に求められます。
シニア社員全員が「働き続けたい」と回答──「自分らしく働ける未来」が成功の鍵に
──「シニア社員自身がそれなりの意欲を求められる」という新たな制度を設計するにあたり、はじめに着手したことは何でしたか。
林原さん:社員が思い描く「60歳以降の働き方」を探ることから始めました。意向を把握しないことには、個々に寄り添った制度設計ができないと考えたからです。
社内ヒアリングを重ねて、独自に分類したのが
- (1)今の職場でバリバリ働きたい
(2)働き方を変え、余裕を持って働きたい
(3)自分の力を外部で試してみたい
(4)新たな人生 好きなことをして暮らしたい
の4タイプでした。(1)(2)の社員に対して、どのような制度で応えればいいのか……当社では2008年に他社の定年退職者を採用する「ゆとり人材制度」をすでに導入しており、それなりの知見はあったものの、試行錯誤の日々が続きました。
──そうしたプロセスを経て、どんな特徴を持つ制度に?
林原さん:一番は、やはり自分のがんばり次第で昇給や賞与が望める点ですね。他ではあまり聞いたことがない、画期的な内容だと自負しています。
また、人材区分は、業務難易度別に3段階に分けました。例えば、最も高度な技術を持つ「熟練者Ⅲ」のシニア社員が、家庭の事情や健康問題などで退職を検討した場合、「熟練者ⅡやⅠという別の働き方もあるよ」と、退職ではなく「働き続ける」という選択肢を提供したい……そんな思いから設定しました。
──スムーズな制度運用のため、開始前に社員に働きかけたことはありましたか。
林原さん:57歳・59歳の社員を対象に、人事面談・キャリア面談のほか、これまでのキャリアの振り返りや60歳以降の職業人生を考える「キャリア リ・デザイン研修」を開催。スキルアップに関しては、社内ニーズの高いITや会計処理関連の講習をスタートさせました。
準備を重ねたおかげもあって、2021年4月の制度スタート時には対象者77名のうち、77名全員に働き続ける意思を示してもらえました。面談やキャリア研修などから「60歳以降も三谷産業で働くイメージ」をしっかり描いてもらえたからだと感じています。
「ご縁を大切にする文化」がシニア雇用推進の原点
──そもそも、なぜ三谷産業ではシニア雇用に積極的に取り組んでこられたのですか。
林原さん:少子高齢化によって人材確保が困難になってきたことも当然ありますが、何よりも「ご縁を大事にする」という企業文化が大きく影響しています。
当社はこれまで、数え切れないほど多くの社員たちに支えられながら、97年の長きにわたり事業を継続してきました。「企業文化の伝承に貢献してきてくれた人とのご縁を60歳で終わらせたくない」という思いが、すべてのシニア雇用施策の根底にあります。
──人材確保が困難になりつつある、というお話がありましたが、社員の年齢層の構成は今どのように?
林原さん:2025年3月末時点のデータでは、社員597人のうち、20代から50代までの各世代がバランスよく在籍しており、60代や70代の社員も一定数います。かねてより、シニアと若手双方の採用両立に努めてきたこともあって年齢構成バランスは極めて良好です。
さまざまな年代の社員が在籍している影響なのか、風通しがよく、フラットな雰囲気なのも当社の特徴です。若手、ベテラン問わず、出されたアイデアや意見は尊重されますし、やりたいことを形にしやすい。こうして新たな制度が次々と生まれ、導入されているのは間違いなく風土によるものですね。
認知症になった役員への対応の後悔が、脳の健康サポートを促した
──社員に長く働いてもらうためには、健康面のサポートも欠かせない要素です。具体的にはどのような支援を行っていますか。
林原さん:健康診断や人間ドックの費用負担のほか、40歳以上の社員には、脳の健康度をセルフチェックできるツールの利用を促しています。
もしかしたら、認知機能の維持・向上に目を向けている企業は、まだ少数かもしれません。当社では “ある出来事”をきっかけに、社員の認知症対策への意識が経営層を中心に高まりました。
三谷産業の歴史を語るうえで欠かせないベトナム事業を、ゼロから開拓し軌道に乗せた役員が、認知症を発症したのは10〜11年前のことでした。もともとは敏腕な人だったのですが、「何度も同じ指示を出す」「もの忘れが激しい」といった症状がだんだんと顕著になってきて。職場の周囲も気づきつつ、50代半ばだったこともあって「加齢が進めば、よくあること」と受け流してしまったんです。
やがて本人が症状を自覚するようになり、休職されました。ほどなくして亡くなったという知らせを受けました。残ったのは「もっと早く病気に気づいてあげたかった。治療に専念してもらいたかった」という後悔でした。
──テオリア・テクノロジーズが提供する「そなえるパッケージ」を導入した背景には、とてもつらい出来事があったんですね。
林原さん:そうですね。ですから対策を講じるのも早かったです。その方が亡くなった数年後には、脳の健康状態が確認できる海外のセルフチェックツールを導入しました。順調に社内に浸透していたんですが、何とそのサービスが撤退、同様のサービスを探し続けていたところ、この度ようやく「そなえるパッケージ」と出会うことができました。
「そなえるパッケージ」の利点は、セルフチェックツールで認知機能低下リスクが懸念された場合、自動的にその社員に脳の健康支援プログラムが案内されること。いわゆる出口まで考え、設計されているところに、このうえない安心感があります。個人的には近い将来、父の日、母の日のプレゼントとして社員だけでなくご家族にも活用できるようになったらいいな、と思っています。
──そのほか、健康状態が不安定になりやすいシニア社員に対して行っている施策はありますか。
林原さん:先ほども触れましたが、家庭の事情や健康状態によって人材区分の変更ができるほか、66歳以上の社員に対しては、産業医による直近の健康診断のデータ確認と面談を行い、就業に支障がないかを確認する場を設けています。
今後は「介護支援」も視野に。社員が安心して働ける環境をさらに広げたい
──スタートして4年が経ちました。制度内容について手を加えた点はありますか?
林原さん:社内外の講師や営業紹介、技術指導などを行った場合、通常の2~3倍の時給額が支払われる「出来高払いオプション」は、当初66歳以上の社員のみを対象にしていたのですが、2年前、60歳以上に拡大。この制度を活用して、活躍の場を広げる社員はさらに増えました。
「キャリア リ・デザイン研修」については、「キャリアは、できるだけ早いタイミングから見つめ直したほうがいい」との考えから、40歳・50歳の社員にも実施することに。
さらに任意の勉強会として「キャリアを考える会」もスタートしました。EXサーベイ(従業員体験調査)の項目で、最も社員のギャップが大きかったのが「キャリア」という言葉の捉え方でした。どうやって埋めればいいのかを社内で議論した末「それぞれが考えるキャリアを相互理解したほうが、組織として発展性があるのでは?」という結論になり、自己開示の場をつくることになったんです。
こうした制度のブラッシュアップも、トップダウンではなく、ボトムアップで進めていけるのが当社のよいところ。多くの社員が自分事として受け止めてくれています。
──最後に、シニア雇用について今後の展望をお聞かせください。
林原さん:今も約80名が「無期限の継続雇用制度」を活用し、現場で活躍してくれています。このペースで制度を運用しつつ、今後は介護支援制度も拡充していく予定です。構想しているのは、専用の相談室の設置や外部の支援機関との連携。介護と仕事の両立をサポートしながら、引き続き大切なご縁を紡いでいきたいです。
(取材・文 福嶋聡美)