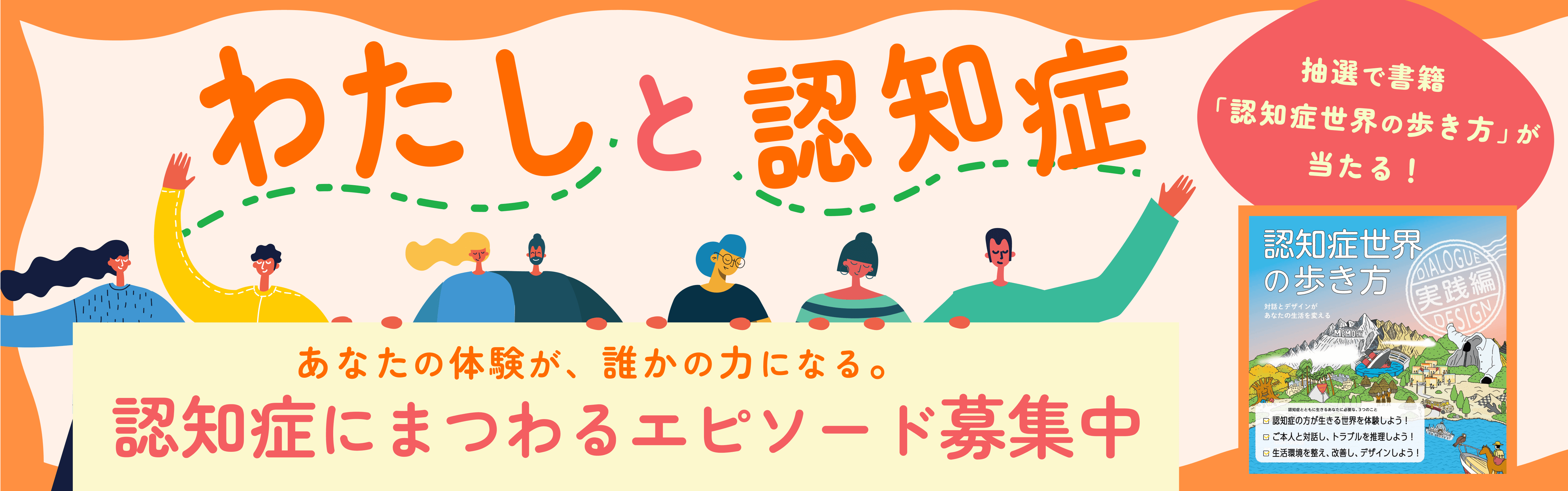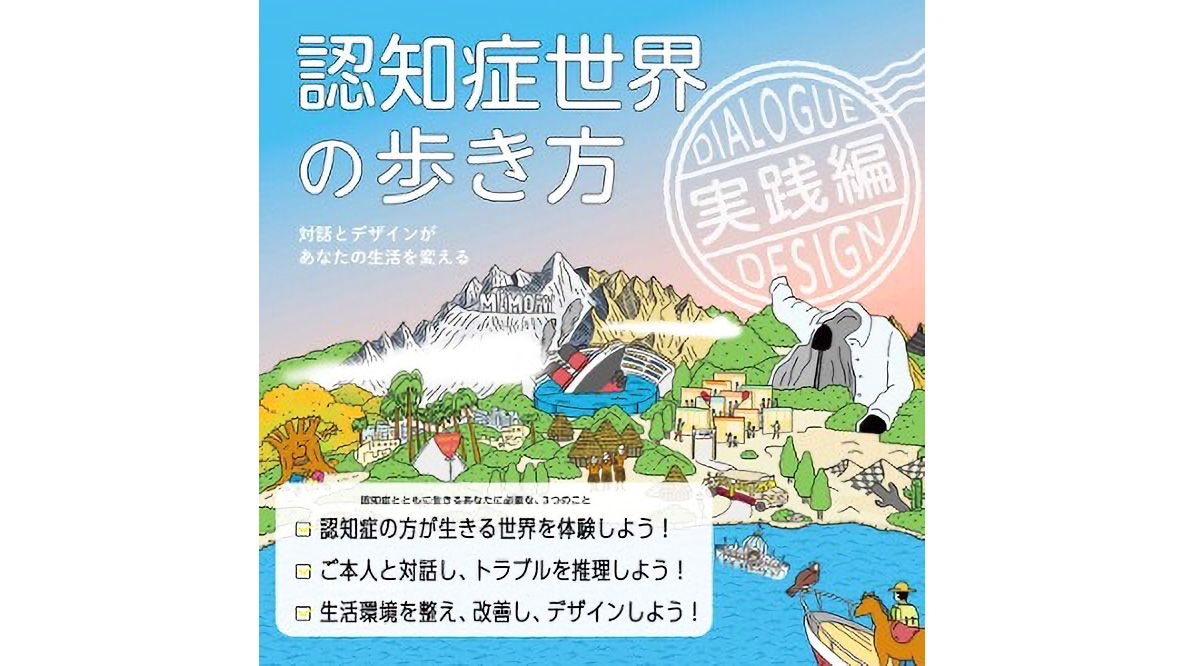お話を伺った方
-

髙波 仁子さん
稲城市役所 福祉部
高齢福祉課 地域支援係 地域統括担当係長 (保健師)
認知症施策担当として、地域の声を聴き、地域の持つアイディアをどう実現するかを日々考えています。モットーは「3倍の価値を創造する」。
-

平野 さちさん
稲城市地域包括支援センターやのくち
認知症支援コーディネーター(認知症地域支援推進員・看護師)
推進員として、相談や家族支援、認知症カフェの運営、認知症関係の講座などを 担当しています。関係機関と連携し、出会い、つながりを大切に活動しています。
-

田島 美穂さん
稲城市地域包括支援センターこうようだい
認知症支援コーディネーター(認知症地域支援推進員・看護師・保健師)
地域で生活する認知症の方とその家族が安心して過ごせるように、さまざまな関係機関と連携して多角的なサポートを実施。認知症の方の声を拾い上げ、市や地域住民と協働して認知症に優しい街作りを目指して活動しています。
東京都の多摩地域南部に位置する人口約9万人のまち、稲城市。1970年代以降の多摩ニュータウン建設や京王線・小田急線の沿線開発に伴い、多摩川流域の住宅地と合わせて人口が急増した地域です。そのため、同じ市内でも地域ごとに高齢化の状況や特性、課題があり、それぞれの地域特性に応じた施策が必要とされています。
地域特性に合わせ、認知症を「予防するもの」ではなく「備えるもの」として捉え、自分らしく生きていくための支援を重視している、稲城市役所高齢福祉課の髙波さん、地域包括支援センターの認知症コーディネーターの平野さん、田島さんにどのような取り組みをされているのかをうかがいました。
稲城市が目指す「認知症が特別なことではない社会」
稲城市の認知症施策について、基本的な考え方を教えてください。
髙波さん:
私たちが目指しているのは、認知症が特別なことではない社会です。認知症基本法の理念に基づいて、住民の皆さんと一緒に理解を深めていきたいと考えています。
特徴的な取り組みとしては、地域包括支援センターに平野さん、田島さんという専任の認知症コーディネーター(認知症地域支援推進員)を配置して、市役所と緊密に連携を図っているところです。市役所だけでは見えないような目線での、住民に近いところの話をきくことができ、施策を充実させることができると感じています。
多様な「顔」を持つまち、稲城:地域特性と高齢化
稲城市の地域特性について教えてください。
髙波さん:
稲城市には、3つの特徴的な地域があります。
まず多摩ニュータウン地域の向陽台、長峰、若葉台。一番早くから開発された向陽台は開発から40年が経って、16年後には高齢化率が50%を超えると予測されています。若葉台は比較的裕福な方も多くて、高齢化に伴って施設入所や転居を選択される方もいます。
それから平尾地域。平尾には1970年代から始まる平尾団地があり、高齢化率が40%を超えていて、経済的な課題も含めた支援が必要になっています。
平野さん:
そして私が担当する矢野口地区は、15年以上前から体操グループなどの住民活動が続いている、地域の繋がりがとても強い地域なんです。同じ市内でも様々な顔を持つ地域があるため、それぞれにあった支援をしていく必要があります。
施策の根底にある考え:「予防」ではなく「備え」
稲城市の認知症施策の特色を一言で言うとなんでしょうか?
髙波さん:
市としては、認知症基本法の理念に則って、「認知症の方が地域にいることが普通の社会」になることを目指していて、私たちもそれを思って今活動しています。
私たちは『認知症予防』という言葉を使わないようにしています。認知症は『防ぐもの』ではなく、『備えるもの』として捉えたい。来るべきものに対して、よりよく自分らしく生きていくための『貯金』をしていこう、そういう考え方で取り組んでいます。
『貯金』とは?
髙波さん:
私たちが思う『貯金』には、認知症に関する知識を持つことや健康管理はもちろん、楽しみや生きがいづくり、地域の方々との交流など、その人その人によって様々な形があると考えています。
地域で育む、稲城らしい取り組み事例
とても素敵な考え方です。具体的な取り組みとその背景を教えてください。
田島さん:
稲城市では現在、認知症カフェの取り組みを三層構造で展開しています。
稲城市の認知症カフェの取り組み
市や地域包括支援センターをベースとした専門的支援の場(包括BASE)。
グループホームや老健など施設で開催することで、専門職や介護職と会いながら安心できる地域密着型の居場所づくり(施設BASE)。
そしてすでにある居場所の人たちが、認知症の軽度の方であれば普通に受け入れるのを目指して、参加者自身が企画運営に関わる自主活動の場(地域BASE)です。
包括BASEの認知症カフェ(オレンジカフェ)はこれまでも通年カフェとして矢野口と向陽台がありましたが、3つ目のふれあいセンター平尾では、住民の声から始まった認知症ケアパス勉強会が定期的な交流の場になって、現在では毎回20名以上が参加する認知症がある人もない人も分け隔てなく集まるカフェに発展しました。
私たち地域包括支援センターの認知症コーディネーターは、相談を待つだけじゃなくて、積極的に地域に出向いています。高齢者だけに限らず、いろんな人が集える場所としてふれあいセンターがあるのですが、認知症の人も受け入れてもらえないかと運営する皆さんと一緒に支援や方法を一緒に話し合っていました。
「じゃあちょっとやってみましょう」というかたちで始まったのですが、「なんでも相談会」の内容だと人が集まりませんでした。そこから再度内容について見直し、通年で認知症ケアパスについての勉強会にしたら、徐々に人が集まるようになったんです。
元々ふれあいセンターに来てくださっている認知症の当事者の方がいて、「ケアパスの内容がわからない」という声から始まったアイディアでした。
毎回のテーマも参加者の声を反映させることで、認知症の当事者やご家族、地域の方々など、様々な立場の方が認知症を語れる場として活用していただいてます。
認知症コーディネーターが地域に入っていって、声を実際に聞いたからこそできることですね。
髙波さん:
もう一つ、特徴的な取り組みの1つが「えほんのつばさ」という市民グループの活動です。これは、認知症予防教室の卒業生たちが中心となって立ち上げた、世代間交流を目的とした絵本の読み聞かせグループです。
市や地域包括支援センターが地域とつなげる役を果たし、今では、保育園や小学校、障害児施設、高齢者の集まりなどで定期的に読み聞かせ活動を行い、子どもたちや地域の方々との交流を通じて、高齢者の方々の社会参加と生きがいづくりを実現しています。参加者の方々からは「子どもたちの笑顔に元気をもらえる」「これがあるから頑張って病気をしても復活したい」といった声が寄せられ、まさに地域における「居場所」「役割」として定着しています。この活動は、社会参加の好例といえますね。
なるほど。生きがいも市が支援しているのですね。
髙波さん:
また、図書館との連携も進めています。市内7つの図書館全てに「認知症に優しい本棚」が設置され、アルツハイマー月間には高齢福祉課とタイアップして特別展示も行っています。認知症疾患医療センターである稲城台病院の医師や家族会とも協力し、本の選書や情報交換会も行いました。
このような企画を通じて図書館を運営する皆さんと交流することで、司書の方も認知症に関する知識や支援の存在を知ってもらうことで頼っていただけるようになりました。図書館に来る方で、毎日来てるけど様子が変だな?図書を貸してあげたけど返ってこないな?と言う時にどうしたらいいかと悩んでいたこともあり、配慮の仕方や地域包括支援センターに繋ぐということを知ったり、また地元の認知症に関するイベントに参加し、市のイベントのアドバイスもくださるようになりました。
アルツハイマー月間の取り組み
地域とつながることで、見守りや支援の輪も自然に広がっていますね。
髙波さん:
市内の中学3年生全員(約750名)を対象とした認知症サポーター養成講座も実施しています。認知症に関する映像や希望大使からのメッセージなど、心に残る工夫を取り入れて、認知症のことはもちろんですが自分の命の大事さにも目を向けてほしいと思っています。今後も一般向けや小学生向けに改善を続けていきたいと担当者で話しています。
認知症サポーター養成講座からチームオレンジへ
今年、担当者で話し合う中で「共生の木」というのをイメージして作ってみたのですが、幹の根元に「認知症サポーター養成講座」があって、次に「ステップアップ講座」を受けてもらい、その後、私たちは「個人支援」「グループ支援」と「まちづくり」という形でチームオレンジを作れたらいいなと思っています。
デザインも工夫を凝らした稲城市の認知症サポーター修了証
担当者として印象に残っている経験や気づきはありますか?
平野さん:
認知症カフェに通われていた方で、印象に残っている経験があります。その方は当初「認知症にだけはなりたくない」と繰り返し言われていました。でも実際に診断を受けた時「ああ、そうか。こんなもんなんだな」と受け入れられ、カフェに来ることで前向きな気持ちになれたとおっしゃってくださいました。
また、お一人暮らしの認知症の男性の支援では、「そんなに心配してもらわないといけないのか?」という言葉に、これまでの自立した生活とプライドを大切にしながら、どう支援していくかの難しさを感じました。日々、認知症支援の難しさを考えながら活動しています。
田島さん:
認知症支援コーディネーターとして最初に担当した方は、ご家族と同居されていましたが外出を拒んでいらっしゃいました。電話などで慎重に会話を重ねていくうちに、カフェに誘うことができ、「こんなに自分の話を人にしていいんだ」と気づかれ、その後はお一人でも通えるようになりました。
私はお手紙をいただくことも多く、「皆様とお話をするだけで元気をいただき、体がスッキリしました」といった内容に、この仕事のやりがいを感じています。
家族会も開いていて、毎回8-10人ほど集まるようになり、介護する家族同士で励まし合える関係性が築けてきているのを嬉しく思っています。
これからの展望:住民のパワーを活かしたまちづくり
地域包括支援センターの役割は今後どのようにしていきたいとお考えですか?
髙波さん:
介護人材の不足が深刻化する中、地域包括支援センターの役割を見直す必要があると思っています。現在、相談件数の約6割が緊急度の高くない比較的軽度な生活相談で、残りの4割が専門的な支援を必要とするケースです。
そこで、軽度な相談は地域の人たちで対応できる仕組みを作り、専門職はより複雑な課題に注力できるようにしたいと考えています。
このためには地域の力も借りながら、専門職の負担を適切に分散し、無理なく長く続けられる支援の形を作ることが大切だと考えています。
地域の人たちが参加しやすくするために、どんな取り組みを考えていますか?
髙波さん:
今、銀行が無人化した跡地の建物に地域包括支援センターの移転を計画しています。ただスペースが広いので、1階には住民が集まって、自己実現できる場作りプロジェクトを進めています。キッチンスペースも作って、若い人からお年寄りまで、包括支援センターも身近に感じてもらいつつ、いろいろな人たちが出会い、お互いに支え合える関係を築いていけたらと考えています。
ニュータウンは効率化してしまい、家族機能が低いところなので、家族機能に変わるようなものができるような場所を提供したいなと思っています。
これからのまちづくりで、特に大切にしたいことは何ですか?
私たちが目指しているのは、住民一人ひとりの知恵と経験を活かし、地域の課題を共に解決していくまちの姿です。そのためには、住民の方々が持つアイデアや技能を地域の財産として活用し、主体的に参加できる機会を増やしていくことが重要です。
来るべき高齢化はわかっている今、地域包括支援センターに相談する内容はここ、地域の住民で解消できることはここ、に変わっていかなければ、市民が地域で自分らしく生きるための支援の手が絶対に足りなくなると思います。
市としてはその未来を見据え、今の良さももちろん活かしつつ、まずは土壌を作っていきたいと考えています。
まとめ
稲城市の認知症施策は、地域の多様性、認知症コーディネーターの積極的な関わり、そして何より住民一人ひとりの力を組み合わせることで推進されていることが大変印象的でした。
これらは、稲城台病院、教育委員会、社会福祉協議会、図書館など、多様な主体との連携によって支えられています。その背景に、高波さんや認知症コーディネーターのお二人が地域に出向き、住民の声やアイデアを拾い上げ、共に形にしていく姿勢が、地域住民からの信頼に繋がっています。
当事者、家族、地域住民、専門職、行政が「手をとる」ことで、誰もが安心して自分らしく暮らせる地域を目指す稲城らしい共生の輪を広げています。