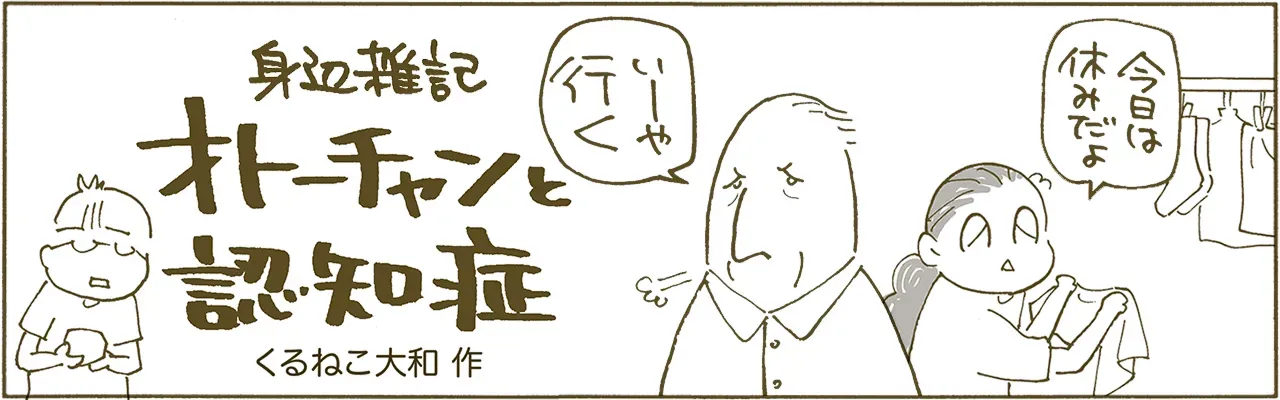脳卒中を発症した後、リハビリテーションによってどこまで回復できるのかや、見通しについて不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、脳卒中のリハビリテーションの具体的な流れや期間、回復の目安について解説します。患者さんやご家族の不安を少しでも解消できるよう、わかりやすく説明していきます。
脳卒中とは
脳卒中は、脳血管の詰まりや血管が破れたり、動脈瘤が破裂したりすることによって脳がダメージを受ける病気です。
主に脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の3つのタイプに分類されます。
脳梗塞は血管が詰まることで脳への血流が途絶え、脳細胞が壊死する状態です。脳出血は脳内の血管が破れてて出血する状態、くも膜下出血は血管にできた瘤が破裂して出血する状態を指します1。
脳卒中による障害
脳卒中による障害は、損傷を受けた脳の部位によって異なります。代表的な症状として、以下のものがあります。
障害の種類 |
代表的な症状 |
|
運動障害2 |
|
|
嚥下障害2 |
|
|
失語症・構音障害2 |
|
|
高次脳機能障害2 |
|
(文献2、3を参考に作成)
脳卒中発症後のリハビリテーションの内容と期間
脳卒中のリハビリテーションは、発症後の時期に応じて急性期・回復期・生活期または維持期の3つに分かれ、段階的に内容が変化します。
発症後の時期とリハビリテーションの目的、具体的なリハビリテーションの内容について表にまとめました。発症後の経過で、どのような内容のリハビリテーションを行うのか目安にしてください。
◎脳卒中発症後のリハビリテーション内容
発症後の時期 |
目的 |
リハビリテーションの内容 |
|
急性期4 |
・深部静脈血栓症※の予防 |
・早期からベットを離れて身体を動かす |
|
回復期5 |
機能回復 |
・歩行訓練 |
|
生活期・維持期2, 5 |
獲得した機能の維持と向上 |
・トレッドミルを使用した歩行訓練 |
※下肢などの静脈に血の塊ができ、血管を詰まらせる病気
(文献2、4、5を参考に編集部作成)
脳卒中発症後のリハビリテーションによる回復の目安
脳卒中発症後に目指せる日常生活のレベルをお示しします。「何カ月後までに、このくらいまで回復することを目標にしよう」と、おおよその目安にしてください6。
発症後の期間 |
リハビリテーションによる回復の目安 |
|
発症~2週間 |
|
|
4週間~8週間前後 |
|
|
3カ月~6カ月後 |
・生活動作の機能の維持 |
(参考文献5、6をもとに作成)
脳卒中発症後は早期からのリハビリテーションが重要
脳卒中発症後は、合併症予防のために早期にリハビリテーションを行うことが推奨されています。
ベッド上で寝たきりの状態が続くと、深部静脈血栓症(下肢などの静脈に血の塊ができ、血管を詰まらせる病気)の発症リスクが高まるためです。
離床でのリハビリテーションが難しい場合は理学療法士による以下のようなベッドサイドでのリハビリテーションが推奨されています4。
- ・下肢を上にあげる運動
・下肢のマッサージ
・下肢の関節運動
身体の動きが制限されている場合は、器具などによって血栓が作られるのを予防します。
いずれも、患者さんの状態によって対応が異なります。重篤な合併症を防ぐために、病院内でのリハビリテーションは必ず主治医や看護師、リハビリスタッフの指示に従ってください。転倒やベッドからの転落などのリスクが上がり危険です。
自宅でできるリハビリテーションのサポート
脳卒中後、家でのリハビリテーションでは、適切な住環境の整備と介護者の心理的サポートが必要不可欠です。
患者さんの安全確保と自立支援を促進するとともに、身体がうまく動かなくなってしまったことへの理解を示し、声掛けの仕方や関わり方を工夫する必要があります。
手すりや介護用ベッドなどの福祉用具を適切に設置し、介護者は「これができるようになりましたね」といった安心感を与えられる肯定的な声掛けを行いましょう。
住環境の調整と介護者の共感的な関わりを組み合わせることで、患者さんの身体機能の回復と心理的な安定を支援できます。
生活環境の整え方
住環境の調整は、安全性確保と自立支援に重要です。
脳卒中発症後に日常生活にどれだけ支障があるかをふまえ、リハビリテーション専門職(理学療法士や作業療法士など)が環境の確認を行い、必要な福祉用具の提案を行うこともあります。福祉用具には、転倒防止や、日常生活の手助けを目的とした以下のものがあります7。
福祉用具の例 |
目的 |
|
手すりの設置 |
浴室やトイレ、玄関などでの転倒予防 |
|
介護用ベッドの設置 |
起き上がり対策 |
|
シャワー用椅子 |
浴室動作の安定 |
|
歩行器 |
・歩行動作の安定 |
(文献7を参考に作成)
介護者の関わり方のポイント
脳卒中後の患者さんには、受容的な態度で共感的な声掛けを行うことが重要です。
脳卒中は身体機能の喪失や社会的役割の変化に伴う否定的な感情が生じやすく、脳卒中後の5年間で約30%の患者さんがうつ病を発症するリスクがあるとされています。
リハビリテーションの際は「ここまでできましたね」という肯定的な声掛けを行い、患者さんの努力を認め、共感と支持を示します。患者さんの感情に寄り添いながら、できている部分に着目した声掛けを心がけ、心理的にもサポートをしましょう8。
まとめ
脳卒中発症後のリハビリテーションは、発症からの時期によって内容が異なります。
急性期のリハビリテーションは、合併症の予防と、関節や身体のこわばりを防ぐのが目的です。
発症後3~6カ月の回復期では、日常生活に戻れるような歩行・食事・排泄・歩行訓練などが行われ、生活期または維持期になると、回復した機能が衰えないよう筋力トレーニングなどを行います。
一般的に、発症後2カ月前後で日常生活動作の回復が期待されます。ただし、回復までの期間は年齢や個人によって異なることに留意しましょう。
病気の発症前と比べると、発症後では日常生活動作に制限が生まれることが多いため、自宅の環境をプロに確認してもらうことが大切です。必要に応じて福祉用具を設置するなど、過ごしやすい工夫をしましょう。