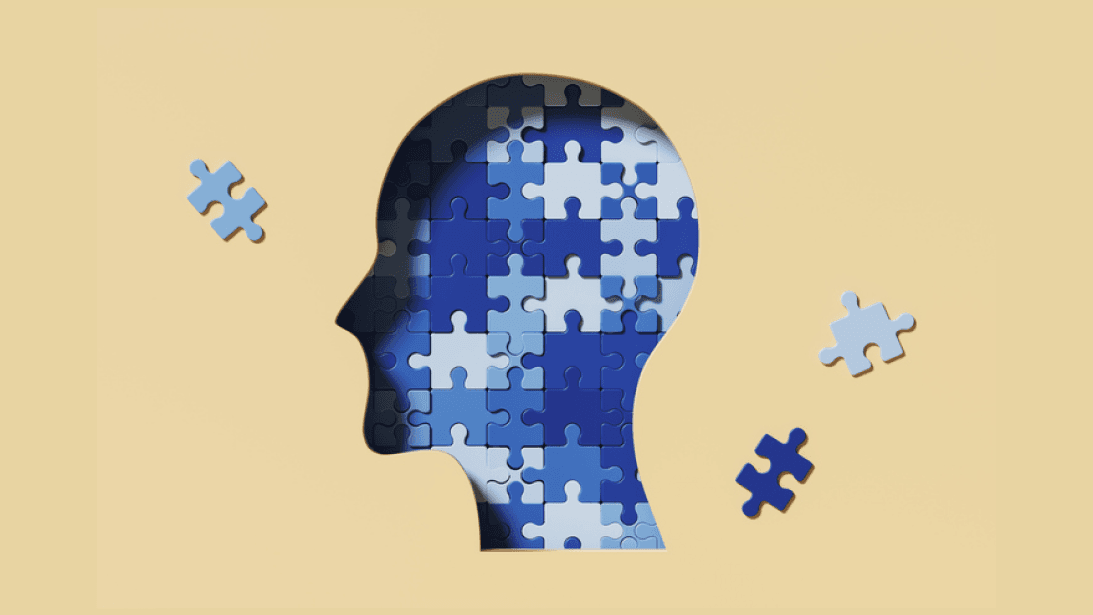「頭が痛くてだるい」「フラフラして歩きにくい」「手や足がしびれる」ただの疲れかな・・・と見過ごしてしまうような違和感が、実は脳卒中の前兆かもしれません。脳卒中は早期発見・治療が予後を左右するため、サインを見逃したくありません。
この記事では脳卒中の前兆から命を守るために知っておくべき対処法まで、わかりやすく解説します。
脳卒中とは
脳卒中は、脳内の血管が詰まったり破れたりすることで、脳に十分な血液が供給されなくなる疾患です。これによって脳細胞が酸素や栄養を得られなくなり、脳の機能が損なわれます。
年間に日本人のおよそ10万人が脳卒中で亡くなっています。悪性新生物(がん)、心疾患、老衰に次ぐ死因の第4位で、寝たきりや介護が必要になるおもな原因の一つです¹。手足のまひや失語症などの重い後遺症があらわれる可能性もあります。
脳卒中の種類
脳卒中は脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の3つに分類されます²。
脳梗塞(のうこうそく)
脳の血管が詰まったり狭くなったりして、手足のまひや言語障害などの症状があらわれます。
脳出血(のうしゅっけつ)
血管が破れて出血し、突然の頭痛やまひ、意識障害を引き起こします。脳梗塞に比べて、後遺症が多く死亡率が高くなる傾向にあります。
くも膜下出血(くもまくかしゅっけつ)
脳の血管にできたコブが破裂することなどで、経験したことのないような激しい頭痛があらわれるのが特徴です。脳卒中のなかでは死亡率が高くなります。
脳卒中の種類ごとに異なる初期症状
脳卒中の症状は、血管が詰まったのか・出血したのか、またそれが脳のどこで起こったかによって異なります。
脳卒中の種類ごとにあらわれる初期症状について、表にまとめました², ³。
【脳卒中の種類ごとの初期症状】
種類 |
初期症状 |
脳梗塞 |
・片方の手足のまひ・しびれ・顔の半分のまひ・しびれ・ふらつき・認知機能低下・言語障害(うまく言葉を発することができない、ろれつが回らないなど)・頭痛 |
脳出血 |
・突然の激しい頭痛・吐き気や嘔吐・片方の手足のまひ・しびれ・顔の半分のまひ・しびれ・認知機能低下・言語障害(うまく言葉を発することができない、ろれつが回らないなど)・意識障害 |
くも膜下出血 |
・突然の非常に激しい頭痛・意識障害(意識の混濁や失神)・吐き気・嘔吐 |
脳梗塞や脳出血に初期段階で気づき適切な治療を開始すれば、リハビリテーションによる回復が期待でき、後遺症を残さずに社会復帰できる可能性を高めます。
しかし、治療が遅れた場合やくも膜下出血の場合は、半身不随や言語障害などの後遺症が残ったり、亡くなったりしてしまう可能性が高くなります。
脳卒中の前兆としてあらわれる5つの症状
下記の5つの症状に1つでも当てはまる場合は、脳卒中を疑いましょう。
1. 片方の手足・顔半分にまひ(基本的に額は含まない)やしびれが起こる。
※手足のみ、または顔のみの場合もある
2. ろれつが回らない、言葉がでない、他人のいうことが理解できない
3. 力はあるのに、立てない、歩けない、フラフラする(身体のバランスがとれない)
4. 片方の目が見えない、物が二つに見える、視野の半分が欠ける(片方の目にカーテンがかかったように、突然一時的に見えなくなる)
5. 経験したことのない激しい頭痛がする
脳卒中の前兆にあらわれる症状は、自分では気づきにくい場合もあります。
周囲の方が「いつもと様子が違うな」「もしかして脳卒中の前兆?」と思ったら、ためらわずに救急車を呼ぶことを検討しましょう。
脳卒中かも?と思ったら
脳卒中の可能性があると思っていても「本当に脳卒中なのか自信がない」「簡単に救急車を呼んでもよいのか」「どこに連絡したらいいのか」など迷ってしまいますよね。
ここでは
・脳卒中の兆候を簡単に確認する方法(FASTテスト)
・脳卒中が疑われるときの対応方法
を紹介します。
一度壊死した脳細胞は戻らないため、脳卒中の対応は一刻を争います。意識障害やまひがあらわれると慌ててしまい、普段のように対応するのは難しいもの。
高血圧や脳卒中の家族歴があるなどリスクが高い方は、あらかじめ目を通しておくことをおすすめします。
合言葉「FAST」で症状をチェック
脳卒中の症状かどうか簡単に確認するときの合言葉は「ACT FAST」。これは、多くの人に脳卒中について分かりやすく伝えるために、米国脳卒中協会がつくった標語です。
FASTはそれぞれ、顔(Face)、手(Arm)、言葉(Speech)、時刻(Time)の頭文字です。顔や手、言葉に異常があらわれたら脳卒中を疑い、症状が出た時刻を確認して、急いで(FAST)行動(ACT)するようにという意味をもっています。
具体的にどのような症状が現れるかについては、表の通りです。
F(Face) |
顔が片側だけ垂れ下がっていないか。 |
A(Arms) |
両腕を上げたとき、一方が下がるか。 |
S(Speech) |
話し方がおかしい、または言葉が出てこないか。 |
T(Time) |
これらの症状を感じたらすぐに救急車を呼びましょう。 |
FASTの診断的中率は80%近いともいわれており、おかしいと思った場合はすぐに試してみるようにしましょう。
対応方法を家族と共有しておきましょう
脳卒中が疑われる場合、119番に電話し救急車を呼ぶ必要があります。救急車を呼んでいる間に注意するポイントは2つあります。
1. 頭を下げましょう
脳の血流を保つため、頭を下げる姿勢を取りましょう。
2. 身体を締め付けるものは緩める
ネクタイやベルトなどの身体を締め付けるものは緩め、呼吸を楽にできるようにしましょう。
脳卒中は迅速な対応が求められるため、
・脳卒中の前兆・初期症状
・症状があらわれたときにすること
・緊急連絡先
・医療機関へのアクセス方法
・持病や普段飲んでいる薬
を家族と事前に確認しておくとよいでしょう。また、脳卒中を予防するための生活習慣について普段から話しておくのも重要です。
脳卒中を予防するためにできること
実は、脳卒中の90%は予防可能といわれています¹。また脳卒中の再発率は非常に高く、再発防止のための生活習慣の管理が重要となります。脳卒中の予防・再発防止のためにできることを実践しましょう。
食生活の改善
塩分は控えめにしましょう。「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によれば、目標量(食塩相当量として)は、成人1人1日当たり男性7.5g未満、女性では6.5g未満と設定されています⁵。
日本人が多く食べる味噌汁は1杯2.0g、ラーメンは汁も含めれば1杯で5.0~7.0gも塩分を摂ることになります。塩分の多いものは摂りすぎないように注意しましょう。
また、塩分を排出するカリウムを多く摂るのも効果的です。カリウムは野菜や果物に多く含まれているため、意識して食べるとよいでしょう。
適度な運動と体重管理
ウォーキングや軽いジョギングなど、無理のない運動を日常生活に取り入れることで肥満や高血圧を防ぎます。運動の頻度は定期的に(できれば毎日)実施し、運動量は30分以上、強度は中等度(ややきつい)の有酸素運動が推奨されています⁶。
忙しい現代人にとって、運動の時間を多く確保するのは難しいかもしれません。しかし、運動習慣は健康維持には欠かせないのです。
禁煙と適度な飲酒の心がけ
喫煙は動脈硬化を進行させるため、禁煙が推奨されています。また、飲酒についても適量を守ることが重要です。「具体的に適量ってどのくらい?」と疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。
そこで、脳卒中と飲酒の関係についてある研究結果を紹介します⁶。
・1日平均3合以上お酒を飲む人は、時々(月に1〜3回)飲む人に比べて、1.6倍脳卒中になりやすい
・1日平均1合未満のお酒を飲む方は、時々飲む方に比べて脳梗塞にかかりにくい
この結果によれば、脳卒中の予防のためには「1日1合未満の飲酒が脳梗塞にかかりにくい適度な飲酒量である」といえるでしょう。
ただし、この結果はお酒を飲まない方に飲酒を勧めるものではありません。飲みすぎないことが重要です。
まとめ:脳卒中の前兆に気づいたらすぐに救急車を呼びましょう
脳卒中は早期発見と迅速な対応が生死を分ける疾患です。前兆となる症状を理解し、自分や家族の健康管理に役立てましょう。
もしも異変を感じた場合には迷わず救急車を呼んでください。一刻も早く適切な治療を受けるのが、後遺症を防ぎ、命を守るために大切なことです。