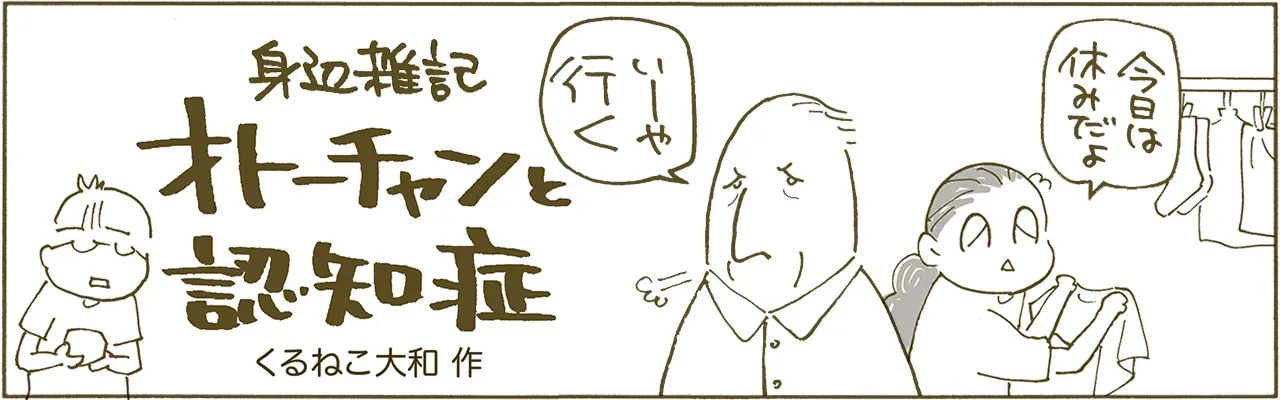6つの基本感情と表情
「表情」と「認知症」の関係をみていく前に、「表情」とその背景にある「感情」の関係を確認しておきましょう。著名な心理学者のエクマンは、基本的な6大感情(幸福、怒り、嫌悪、悲しみ、驚き、恐怖)が存在し、それらを反映した表情が現れるという説を提唱しています1。
では、その6大感情の異常にはどのようなものがあり、どのような表情として表現されるのでしょう。いくつかのパターンがあると思いますが、ここではポジティブ/ネガティブのいずれか一方にシフトしてしまう(かたよってしまう)、あるいは感情の変化がなくなってしまう状態に注目します。
ネガティブシフト(⇒怒り・嫌悪・悲しみ…)
典型的なのがうつ病の患者さんで、抑うつ気分や悲しみが強く、幸福感が減ります。
表情:暗い表情となり、悲しそう、憂うつそうに見えます。場合によっては涙もろくなります。
ポジティブシフト(⇒幸福感)
幸せそうで「多幸的」(深刻味に欠ける)になったり、気分が高揚していわゆる“ハイな状態”になったりします。そう病の患者さんなどにみられます。
表情:幸福感に満ち、ニコニコと楽しそうな表情になります。
感情がフラット(平板)に
「アパシー(apathy)」と呼ばれる状態で、一般的には「意欲低下」と訳されます。「無感情」あるいは「感情の変化が乏しい」と表現することもできます。
表情:表情が乏しくなる、あるいは能面のような無表情になります。
アパシー(意欲低下)と認知症
アパシーについてもう少し説明しながら、認知症と表情の関係を整理していきます。
認知症、特にアルツハイマー型認知症では、病気の初期から記憶力や注意力が低下します。また、認知症全般にわたり、やはり初期からアパシーが認められることもよくあります。無気力・無感動のために無表情になりますが、表情だけがアパシーのサインではありません。私たち医師は、こちらからの呼びかけに上の空だったり、言われないと何もしなかったり、その人の様子を総合的にみてアパシーと診断します。
アパシーとネガティブシフト(うつ状態)との違い
認知症にうつ状態が伴うことも少なくありません。認知症の初期症状としてうつ状態になることもありますし、老年期うつ病から認知症に移行する場合もあります。
認知症や老年期うつ病に関する診療では、うつ状態とアパシーを区別することが重要です。うつ状態もアパシーも、共通して興味や関心の低下が認められます。ただ、うつ状態は背景に悲しみ、憂うつ、焦り、自分を責める気持ちなどがあり、それが表情に表れます。一方、アパシーの場合は感情の不安定さはなく、前述したように無表情になります。
アパシーとポジティブシフト(そう状態)との違い
認知症の人の多くは基本的に多幸的です。悲しそう、憂うつそうにはみえず、むしろ幸せそうな表情になります。特にアルツハイマー型認知症の人は多くの場合、ケロッとしていて多幸的です。
では、テンションが高い「軽そう状態」なのかというと、そうしたケースは少数です。ハイな状態の人は動き回ったり、夜も眠らなかったり、とても活動的ですが、アルツハイマー型認知症では言われないと何もしないなどアパシーの状態が目立ちます。
表情の変化は認知症の初期からみられやすい
認知症の初期症状として感情変化、表情変化がみられることがあります。さらに前段階、健康と認知症の間のグレーゾーンにあたる軽度認知障害(MCI)の時期に、記憶や注意など認知機能の障害よりも、むしろうつ状態やアパシーなどの精神症状が前面にでるケースもあると思います。
認知症のタイプ別 感情・表情変化の特徴
感情変化・表情変化は認知症の可能性を疑うひとつのヒントになりえます。ただ、どういう表情だったらどのタイプの認知症というように、表情の特徴が病気の診断に直結するわけではありません。うつ状態にしろ、アパシーにしろ、多幸的にしろ、特定の認知症に限らず広く認められる精神症状なのですから(これを疾患特異性がないといいます)。
そのことを前提としつつ、「強いていえば」ということで、それぞれのタイプの認知症でみられる感情変化、表情変化の傾向を紹介します。
アルツハイマー型認知症 傾向⇒幸せそうな表情
他のタイプの認知症に比べ、感情・表情も含めて変化の程度は少ない印象です。前述したように基本的に多幸的になります。
レビー小体型認知症 傾向⇒暗く、悲しそうな表情
アルツハイマー型認知症に比べてうつ状態(悲哀感、憂うつ感)が強い傾向があります。
前頭側頭型認知症 傾向⇒無表情
診察室で医師の呼びかけに対してまったく上の空だったり、無関心だったり、アパシーの状態の人が少ながらずいます。
血管性認知症 傾向⇒怒っている表情
脳のどの場所の血管にどういう障害があるかによりますが、全体的に他の認知症に比べて怒りっぽくなる傾向がみられます。
身体的原因による表情の変化
感情変化とは異なる病気の特徴が表情・顔つきにでることがあります。
レビー小体型認知症 傾向⇒硬い顔つき、乏しい表彰変化
レビー小体型認知症では、「パーキンソン症状」といってパーキンソン病によく似た運動障害がみられることが少なくありません。たとえば、体が固くなり、動作がゆっくりになりますが、それにあわせて顔つきが硬くなったり、表情の変化が乏しくなったりすることがあります。
進行性核上麻痺 傾向⇒眼球運動障害
頻度はまれですが、認知症の原因となる病気のひとつです。眼球を上下方向に動かすことが困難になる、首がうしろにそっくり返る、といった顔および上半身の異常が認められると医師は進行性核上麻痺を疑います。
AIが会話や表情に基づいて認知症診断を支援
いったん表情から離れ、「認知症」と「会話」の関係について触れます。
慶應義塾大学医学部 精神・神経科学教室では、高齢者と医療者の自由会話文に基づいて、AI(人工知能)が認知症の可能性を検知する「会話型 認知症診断支援AIプログラム」を開発しました2。現在、医療機器としての実用化に向けて調整を進めているところですが、臨床試験では認知症かそうでないかを約8~9割の確率で識別できています。
特定の課題に答えてもらうのではなく、自由な会話によって認知症のスクリーニング(可能性のある人のふるい分け)を行うので、検査する側に高い専門性は求められません。一般の内科や整形外科など、かかりつけ医のクリニックでも10分程度おしゃべりをし、AIが認知症やMCI(軽度認知障害)のリスクがありそうだと判定したら、認知症の専門医療機関に紹介する──そのような流れができるのではないかと期待しています。
慶應義塾大学では、会話音声や表情などのデータを組み合わせることで、AIが高い精度でうつ病と認知症を区別できることも実証しています3。したがって、表情による認知症の診断支援がある程度まで行われるようになっても何の不思議もないと思います。
AIが教えてくれる、「何かおかしい」という気づきの重要性
AIによる認知症の診断が有望であることは容易に想像できます。しかし、AIが何をもって認知症と判断しているのかはわかりません。そこがわからないのがAIであって、「このように判断しています」と言葉にできるのなら、逆に人間にだってできるわけです。
私たち医師は、患者さんと対面していて、何かおかしいと感じることがあります。何かが違う……それは経験に基づく感覚で、医師本人にも理由を明確に説明できません。勘や経験のようにいわれることもあります。AIが捉えているのはまさにそのような部分であり、AIは私たちの感覚に何かしらの根拠があることを示しているのだと思います。
同様に、受診に付き添ってこられたご家族が、「うちのお父さんがいつもと違う」といった訴えをされることがしばしばあります。医師が「どこが違うのですか?」と聞いても、「何かおかしいんです」としか答えられません。逆にいうと、「ここがおかしい」と説明できるようなら、認知症がかなり進んでしまっているともいえるでしょう。表情も含め、言葉にはできないが家族だからこそ気づく微細な変化というものがあり、認知症の早期発見のひとつの手掛かりになると私は考えています。
(参考文献)
1) P.エクマン、W.フリーセン:表情分析入門、表情に隠された意味をさぐる,工藤力訳,第1刷,誠信書房、1987.
2) Horigome T, et al. Sci Rep. 2022; 12(1): 12461.
3) 平成29・30年度厚生労働科学研究費補助金(政策科学総合研究事業(臨床研究等 ICT 基盤構築・人工知能実装研究事業))分担研究報告書. 研究分担者 岸本泰士郎